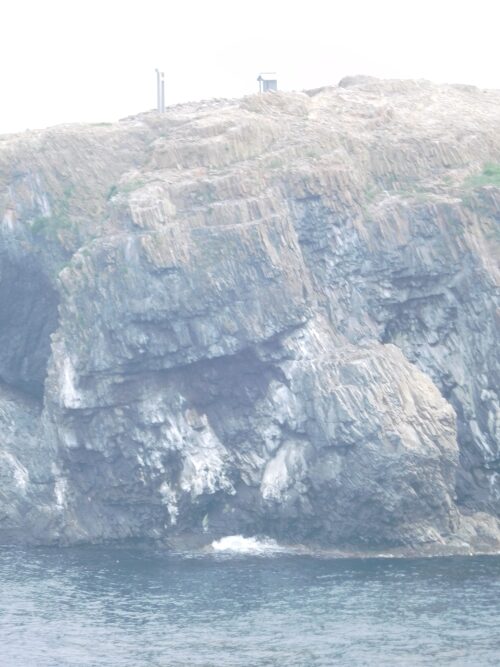こんにちは、みちょるびんです♪
前の週の金曜日に急遽、翌1週間の夏休みをとることになったみちょるびん。幸運にも空きが出ていた寝台特急「サンライズ出雲」の寝台Aのチケットをゲット、それを発端に出雲旅行を計画した。結局は「サンライズ出雲」は運休となり乗れなかったが、代わりに飛行機に切り換え旅行を決行。当初の予定ではJR出雲市駅からその日宿泊予定の「日御碕灯台」までは、直通バスで移動することを考えていたが、バスは途中の「出雲大社」までしか行かないことが判明。2時間の空き時間ができてしまったため、タクシーを利用したのだった。そうして出かけた日御碕。昼食のあとは早速「日御碕神社」をお参りした。
~☆~・~☆~・~☆~・~☆~・~☆~・~☆~・~☆~・~☆~・~☆~・~☆~・☆~
「日御碕神社」でのお参りを終え、元来た道を戻った。
そして、ウニ丼のお店の角を左に折れて、少しワイルドな感じの木の生い茂った道に入って行った。
ホテルでもらった観光マップの通りなら、鳥見台に着くはずだった。
すぐに視界が開け、鳥見台と思しき場所が現れた。
鳥見台――鳥を見るための場所ということだから、主にウミネコを見学するためのものかも知れなかった。
柵で囲われたその場所の左手にはウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されている「経島」が見えた。
鳥見台からは海岸線に沿って遊歩道が設けられていた。
遊歩道を少し歩くと、展望の良い「ひのみさき夕日展望台」に到着した。
マップには親切に、季節によって異なる日没方向が記されており、ここから地平線に沈む夕日が臨めるということを示していた。
日御碕の海岸の地質について説明された看板もあった。
日御碕の海岸の地質は、縦に連なる断崖が特徴とのこと。
ここの岩石はドームの形をした貫入性の流紋岩でできており、1,600万年前にマグマが冷えて形成されたものなのだそうだ。
解説看板にあったとおり、足元にあった岩の断面は不規則な五角形や六角形になっているのがよくわかって面白かった。
この辺りの地形は柱状節理になるのだそうで、節理とは、岩石に表れる規則正しい割れ目のことを言うので、柱の形をした割れ目ということになる。
岩はこれらの節理に沿って簡単に割れやすいため、日本海の強い波の作用によって独特な幾何学的な形ができあがったのだそうだ。
「経島」も同様に柱状節理の岩でできており、それがちょうどお経の巻物を積み重ねたように見えることから、「経島」と名付けられたと言われているらしい。
そういえば、これに似た風景を「東尋坊」で見た記憶があった。
「東尋坊」は、サスペンスドラマで犯人が追いつめられるシーンに登場することでお馴染みの、あの断崖絶壁で有名な場所である。
福井県坂井市三国町の越前加賀海岸国定公園内にあり、断崖絶壁は約1km続く。
海食で岩肌が削られた高さ約25mの岩壁は、天然記念物に指定されている輝石安山岩の柱状節理で、輝石安山岩の柱状節理は韓国の金剛山、スカンジナビア半島のノルウェーの西海岸を含めて世界で3カ所しかない地質学的にも貴重な自然遺産ということだった。
因みにイギリス北アイルランドの世界遺産、ジャイアンツ・コーズウェーも柱状節理で有名だけど、こちらは玄武岩。
岩の構造が柱状節理であるので景観が似ているように感じられたのは当然なわけだが、どうやらそれを構成する鉱物の種類によっていろいろ分類されているらしい。
この「ひのみさき夕日展望台」からは一帯が柱状節理である様子がよくわかったので、夢中になってカメラに収めた。
芝生に足を踏み入れたときに、足元で何かが弾けたように見えた。
何だろうと思って顔を近づけてみるとショウリュウバッタだった。
斜め上に尖った頭部が特徴の、日本に分布するバッタの中では最大種と言われている黄緑色のバッタね。
子供の頃はよく見かけたものだったが、ショウリュウバッタを見たのは何十年ぶり・・・というレベルの久しさである!
写真を撮ろうと歩み寄ると、実は何匹もいたようで、またパッと弾け散った。踏まないようにそろそろと歩いて芝生の外に出た。
そこから更に進むと「柏陵園」と言うところに出た。
日本海に面し、柱状節理の岩の上で、北西の風に耐え倒れるようにして大きく育った松林をそう呼んでいるとのこと。
松の間を進むと、いよいよ「日御碕灯台」が見えてきた。
「日御碕」のランドマークのお出ましである!
(つづく・・・)
以上、みちょるびんでした!